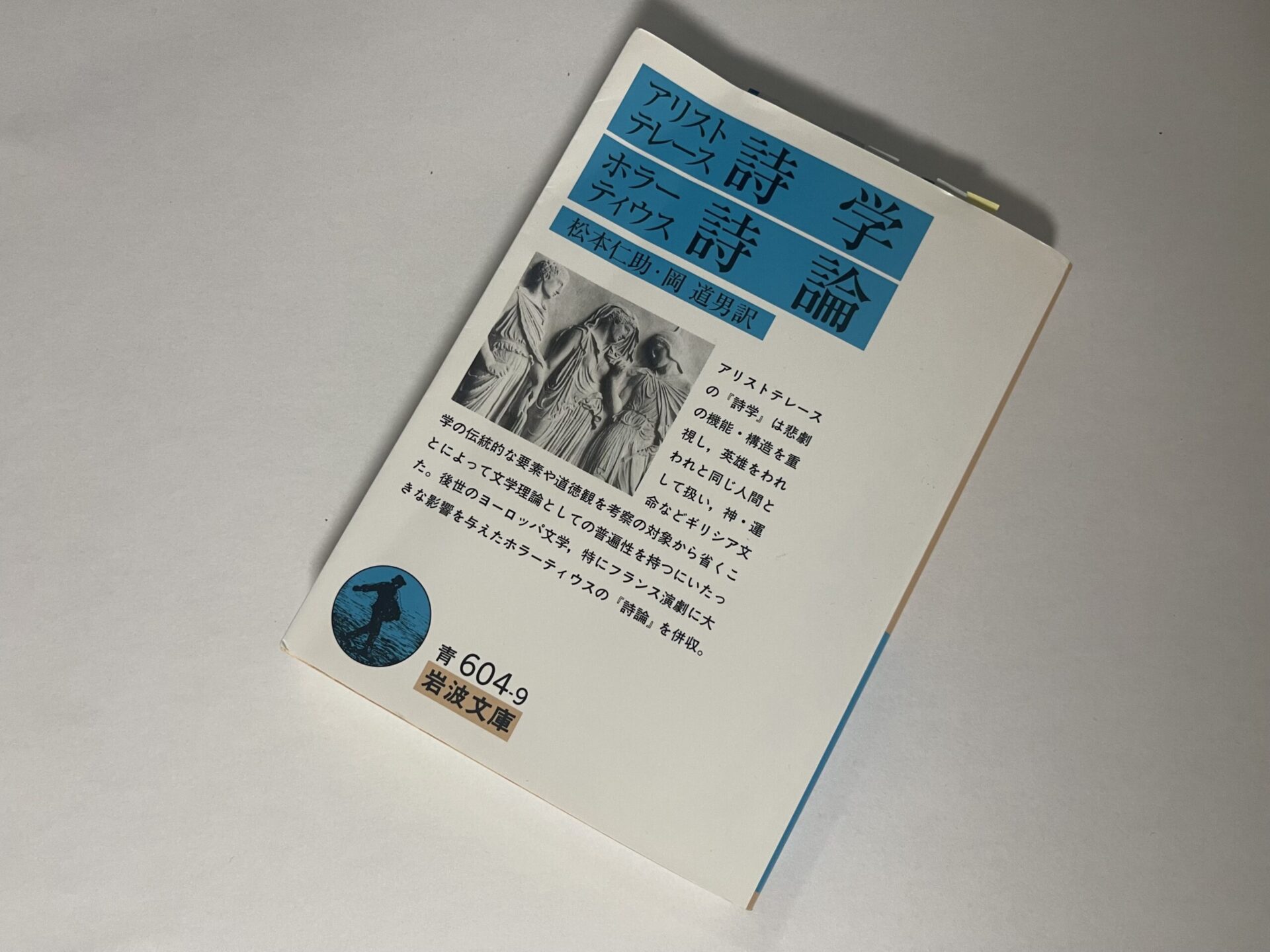「詩」という語を辞書で引いてみると「自然や人事について起こる感動などを圧縮した形で表現した文学」(小学館『新選国語辞典』第七版)とあります。
たとえば谷川俊太郎さんの詩とか、松本隆さんの詩(歌詞)とか。たとえが最近すぎるな。
アリストテレス(384-322 B.C.)が『詩学』で著した「詩」とは要するにフィクション・叙事詩・劇詩(戯曲)など文学全般のことで、本書では詩の目的や機能が理論的に説かれています。
詩作自体がセンスのように語られることがありますが、本書はセンスの話は皆無。詩作の思想や語法や制作技術、テクニックがしかつめらしく書かれています。
演劇をはじめ、創作に関わる人は知っておいたほうがいい基礎理論が満載です。
アリストテレスは詩作のなかでも特に悲劇について深く掘り下げています。
悲劇の原点であるギリシャ悲劇の数々は神話や伝説を題材とし、舞台上に神(役)が現れたり、神が出来事に影響を及ぼすような描写がある。
アリストテレスは神や偶然(天変地異)の介入を否定し、悲劇は人間の行為のミーメーシス(再現)であり、あやまちから生じる結果を生むものと定義します。
不幸に陥るのは善人や悪人といったいかにものキャラクターではなく、あやまちを犯しそうな者でなくてはならない、と。
なぜならそうでなければ、観客に「おそれとあわれみ」をもたらさないから。
まぁ確かにサスペンスドラマでハラハラさせられているところを、神様が登場して事件が解決したら観客・視聴者はふざけんなってなる。
当然と言えば当然だけど、よくよく顧みると神が描かれなくても、神の代替的なキャラクターって映画にもテレビドラマにもマンガにもたくさんいますね。
この人が出てくれば解決! みたいな。
よきにつけ悪しきにつけ、そういうご都合主義的な面で客はフィクションとして安心して観ていられる。
それは一過性の快感をもたらすかもしれないけど、真に人間の営為を描いているかというと違います。
大衆的なエンタメのなかでも演劇は普遍的なものを追求することにおいては最も可能性があるジャンルなのでしょうね。
岩波文庫版である本書の後半に収録された『詩論』は、詩人のホラーティウス(65-8 B.C.)によるもので、『詩学』よりももう少し平易な言葉で書かれているのが特徴。
「読者をたのしませながら教え、快と益を混ぜ合わせる者が、万人の票を獲得する」といった至言や、詩作におけるちょっとしたコツが書かれている印象です。
本編よりも注釈のほうがページ数が多いのが哲学書あるあるですが、ワシの場合は本編は本編で、松本仁助さんと岡道男さんによる訳注だけは単独で(別にして)読みました。いちいち照合していられない。
半分以上ちんぷんかんぷんですが、浅学でも勉強しないよりマシってことで。
 |
詩学(アリストテレース) 詩論(ホラーティウス) (岩波文庫 青604-9) [ アリストテレース ] 価格:1155円 |
![]()
 |
価格:1254円 |
![]()
 |
ドストエフスキーの詩学 (ちくま学芸文庫) [ ミハイル・ミハイロヴィッチ・バフチン ] 価格:1760円 |
![]()